
創業は大正9年(1920年)。平成11年に杜氏制を廃止し、蔵元家族中心の現在の体制で20年を迎えています。酒造計画等の工夫に基づき無駄のない、確実かつ丁寧な仕事をすることを信条に社員全員が力を合わせて日本酒「石鎚」を醸しています。
銘柄:石鎚
サイト:https://www.ishizuchi.co.jp/
代表者:代表取締役社長 越智浩 様
Q 導入ポイントは?
現場の負担低減のため。AB直線のグラフ表示を使い酒造りに活かす。
本システムの導入事例にご協力いただきました。ぜひあわせてご覧ください。
石鎚酒造 代表取締役社長 越智様 >>

1900年(明治33年)創業の株式会社福井酒造場(三重県伊賀市)の清酒製造業を引き継ぎ、酒事業に参入しました。三重の豊かな風土が育む、清らかな水と良質な酒米を使用し、テロワールに根差した酒造りを行ってまいります。
また、清酒醸造工程の機械化と温度管理など品質管理を徹底することでいつでも作りたてのお酒を提供できる四季醸造を行っています。
銘柄:福和蔵
サイト:https://www.fukuwagura.jp/
製造責任者: 安田 裕幸 様
Q 導入ポイントは?
経過簿の測定の自動化、データ化による管理化、経過簿の自動作成による事務作業の軽減、PC・スマホによる確認のしやすさ。

創業1892年(明治25年)。伊賀盆地のほぼ中央、周囲は白鷺が飛び交う豊かな田園に囲まれた地で、厳寒期のみに出来るだけ手作業にこだわり、地域にねざした少量の酒造りを行なっております。原料米は三重県産、伊賀産の酒米と地元契約栽培米を主に使用し、「服部半蔵」ゆかりの地「伊賀上野」にて、その名を冠した「半蔵」を醸しています。近年、酒質向上に努め様々な賞を受賞。また、昔ながらの木桶仕込み等も行ないながら蔵内の井戸水を使い、幅広い味わいの丁寧な酒造りを心がけております。
銘柄:半蔵
サイト:https://www.hanzo-sake.com/
杜氏:大田有輝 様
Q 導入ポイントは?
製麹を従業員が担当する際に遠隔確認がおこなえるようにし、負担低減につなげるため。

安政元年(1854年)創業。蒸しは甑、麹は箱麹、仕込みは1,200kg前後の小仕込み、搾りは木艚袋搾りを今に残し醸造しております。当酒蔵は、江戸蔵から昭和の木造建築が立ち並んであります。仕込み蔵は昔ながらの知恵が十分に活かされて設計されております。また量を造る時代から個性のある酒造りに変わり、多く並んでいた使われていないタンクを出し、金亀ギャラリー、金亀酒蔵ホール、試飲スペース、蔵周辺の空き民家を活用し、田舎料理店など古くても新しい活用も試みております。
銘柄:金亀、大星
サイト:https://kin-kame.co.jp/
代表取締役:岡村 博之
Q 導入ポイントは?
手持ちのスマートフォンにて麹、醪、酒母品温がどこでも居ながらにして複数人が確認できる。記帳内容(日誌)も見られ、データを数年蓄積すれば同じ画面でグラフや数字を比較できる事は嬉しい。

創業者の小山屋又兵衛は灘・伏見で酒造りを習得後、1808年(文化5年)に武蔵野国北足立郡指扇村字下郷(現・さいたま市西区指扇)に良質な水が湧き出ることを発見し、酒造りを始めました。創業以来、築き上げてきた酒造技術を大切に守り、品質第一主義をモットーに、お客様の多様なニーズにお応えするとともに、安心・安全で美味しいお酒をリーズナブルな価格で提供することを心掛けて参りました。
銘柄:金紋世界鷹、東京盛
サイト:https://www.koyamahonke.co.jp/
Q 導入ポイントは?
麹品温確認の低減で夜間品温確認負担減少。
スマホ、ipadで分析値、品温 等の状況確認が出来ることで、出勤日数、電話連絡の減少。

1892年(明治25年)創業。蔵のひとたちが苗作りから田植え、収穫までおこなって育てた米と、八ヶ岳の上質な伏流水を使い、手造りで醸しています。地酒の味わい、喉越し良く、五味(甘味、酸味、辛味、苦味、渋味)を供えた爽やかな酒造りを大切にしています。
銘柄:佐久乃花
サイト:https://www.sakunohana.jp/
代表者:代表取締役 高橋 寿知 様

1686年(貞享3年)鶯宿梅蔵元、鈴木家を母体として昭和46年5月に設立。臥龍梅は一般販売用も手抜きをせず、鑑評会出品酒と同じ吟醸小仕込みによって造られています。地元の酒屋やスーパーの棚には米の種類や精米歩合の異なるさまざまな臥龍梅が並び、身近に楽しめる旨いお酒として親しまれています。
銘柄:臥龍梅(がりゅうばい)
サイト:http://www.garyubai.com/
代表者:代表取締役社長 鈴木 克昌 様
Q 導入ポイントは?
品温データの取得して離れた事務所と蔵の間でデータを共有したり、もろみの関連データを蓄積して会社の資産とする方法を検討していました。スマホで品温が確認できる機能は、宿舎に寝泊りする蔵人の負担を軽減しています。
本システムの導入事例にご協力いただきました。ぜひあわせてご覧ください。
三和酒造 代表取締役社長 鈴木様【経営者の立場から】 >>
三和酒造 杜氏 多田様【酒造現場で働く立場から】 >>

創業1903年(明治36年)12月。「南部杜氏発祥の里」として知られる岩手県紫波郡紫波町にある酒蔵です。初代廣田喜平治がこの地で当時評判だった造り酒屋を譲り受け、今日まで酒造りを続けています。 地域・地元のお祭りや祝い事を始め、多くの酒席に花を添える一献として「廣く多くの人々に喜ばれる酒」として生まれた『廣喜』は、今でも当蔵を代表する銘柄として親しまれています。
銘柄:廣喜
サイト:https://www.shiwa-shuzoten.com/
代表者:田中 文悟 様

安永6年(1777年)創業。「美味しいお米だから美味しいお酒になる。」をモットーに、全国的にも珍しい全量食用米のお酒づくりをされています。地元丹後のコシヒカリと湧き水で「ご飯のような日本酒」をめざしています。
銘柄:白木久(しらきく)
サイト:https://shirakiku.shopinfo.jp/
代表者:代表取締役 白杉 悟 様
Q 導入ポイントは?
品温を自動計測して、グラフまで表示できるところです。スマホで常に品温を確認できたり、指定した品温になったときアラートが通知されることで、蔵に不在時もゆっくりすすむ発酵のわずかな変化やタイミングを把握しやすくなります。

明治6年(1873年)創業。染物業を営んでいた初代貞造が酒造業を始めたのが鶴見酒造の歴史の始まり。
南部杜氏が醸す技、手作りによる製造の良さを守りつつ、近代的な品質管理とを巧みに調和させ、米の旨味を酒の中に充分生かしたコクのある、より良い日本酒の開発に取組んでいる。
銘柄:我山、山荘、神鶴
サイト:https://www.tsurumi-jp.com/
AWS サイトに鶴見酒造様のもろみ日誌クラウド導入事例が掲載されました >>

1680年(延宝8年)創業。飛騨に商いのため出店を構え、飛騨の人情の細やかさ、自然の美しさ、風俗の麗しさに魅かれて、この地に住み着き、物品販売のかたわら日本酒造りをはじめました。飛騨の自然を愛し、人情を愛した日野屋佐兵衛の心意気を、酒造りを始めてから八代目になる現代まで脈々と受け継ぎ、飛騨の自然の恵みで育った酒造好適米「ひだほまれ」、飛騨山脈からの地下水をもちい、自家精米にこだわり、飛騨の酒を造る天領へと成長を続けています。
銘柄:天領
サイト:https://www.tenryou.co.jp/

弘化元年(1844年)創業。「国の繁栄を願い、それとともに我が酒の盛んなること」を望む気持ちを込めて「國盛」と命名し世に送り出しました。環境が変化する中でお客様のニーズは移り変わります。伝統的で高い品質の日本酒を提供する事はもちろん、新しい酵母や麹菌の開発、今までにない仕込み方法で造った“新日本酒”を提案し続ける企業となります。
銘柄:國盛
サイト:https://www.nakanoshuzou.jp/
代表者: 代表取締役社長 中埜 昌美 様
Q 導入ポイントは?
酒造りデータの共有と蓄積による技術の継承。現場業務の負担軽減。

「日々の生活の中で親しまれる名酒」を目指しています。出荷量の95%超が純米醸造であり、純米酒に特化しています。蔵の風土に合った、米の旨味を活かした酒づくり、蔵の個性を大事にしていきたいと考えております。
銘柄:黒牛
サイト:https://kuroushi.co.jp/
代表者:代表取締役 名手孝和 様
Q 導入ポイントは?
品質の安定と向上、製造職員の負荷軽減、技術習得の促進効果があります。
生産性向上、製品開発や企画に活用できることを目指しています。

安政2年(1855年)創業。昔ながらの酒蔵を守り、品質の良い美味しい日本酒を届けたいと願っています。時代が変わり、酒の飲み方にも変化が訪れていますが、伝統を守りつつもお客様から新しいと言っていただけるよう、挑戦する心を忘れない熱い酒蔵です。
銘柄:徳正宗
サイト:https://www.tokumasamune.com/
代表者:代表取締役社長 萩原 康成 様
Q 導入ポイントは?
業務が合理化できるところです。

寛永12年(1636年)屋号を「足名屋」とし、駿府城からほど近い場所で創業。明治9年(1876年)江戸時代には東海道の宿場町として栄えた岡部町に蔵を移転。現存する造り酒屋の中では静岡県で最古、全国でも31番目に古い歴史を持つ酒蔵です。「静岡のヒト・食文化との調和」を第一に考え、感謝の心と丁寧な手仕事で酒を醸します。
銘柄:初亀
サイト:https://www.hatsukame.jp/
代表者:社長 橋本謹嗣 様
Q 導入ポイントは?
データの蓄積と、現場の負担軽減。

大正10年(1921年)に創業。酒造りでは地元の最高のお米、兵庫の特産物である兵庫県特A地区産山田錦を40年以上使い続けております。龍力の歩みは挑戦の歴史です。いち早く全量酒造好適米に取り組み、いち早く大吟醸酒に取り組んできました。「米の酒は米の味」を基本理念として酒造りを行っています。山田錦を土壌から研究し、土壌違いによる発酵、味わいの違いを追究しています。また、これからの時代を考え、長期熟成酒にも取り組んでいます。
銘柄:龍力
サイト:https://www.taturiki.com/
代表者:代表取締役社長 本田 龍祐 様
Q 導入ポイントは?
蔵の働き方改革を考え、夜間の負担の軽減が導入ポイントです。
スマホへのアラームは非常に役に立っています。

1893年(明治26年)創業。日本酒の命といえる「米」と「水」。御代桜醸造では、地元岐阜県美濃加茂市産の契約栽培米の他にも、全国から選りすぐりの原材料を取り寄せて使用しています。そして、“よい水から名酒が生まれる”と言われますが、酒蔵敷地内の井戸から清冽な木曽川伏流水を汲み上げて使用しています。 日本酒は嗜好品なので、美味しさには様々な種類がありますが、品質管理には出来る限り妥協したくないと考えています。全てはお客様の笑顔の為にー
銘柄:御代櫻・津島屋
サイト:https://www.miyozakura.co.jp
代表取締役 渡邉 博栄 様
Q 導入ポイントは?
PC・スマホによる品温確認のしやすさや、指定した品温でのアラート通知機能は、麹室入室回数の軽減や夜間温度見回り回数の軽減等、製造現場の負担軽減に大変効果的です。

舟屋の建ち並ぶ京都府与謝郡伊根町にある、創業宝暦4年(1754年)の造り酒屋です。女性杜氏ならではの発想で生み出された「伊根満開」は、ロゼワインのような色と味わいをもつお酒で、女性に人気です。
銘柄:京の春、ええにょぼ、伊根満開
サイト:https://kuramoto-mukai.jp/index.html
代表者:代表取締役社長 向井 崇仁 様、杜氏 向井 久仁子 様
Q 導入ポイントは?
品温計測の手間が省ける製品の中で、もろみ日誌は税務署の帳票に対応していてデータ管理を一本化できるところが決め手でした。1.5mあるスティックタイプの温度センサーは、仕込みの初期でももろみにしっかり挿さって計測できるのがいいと思います。
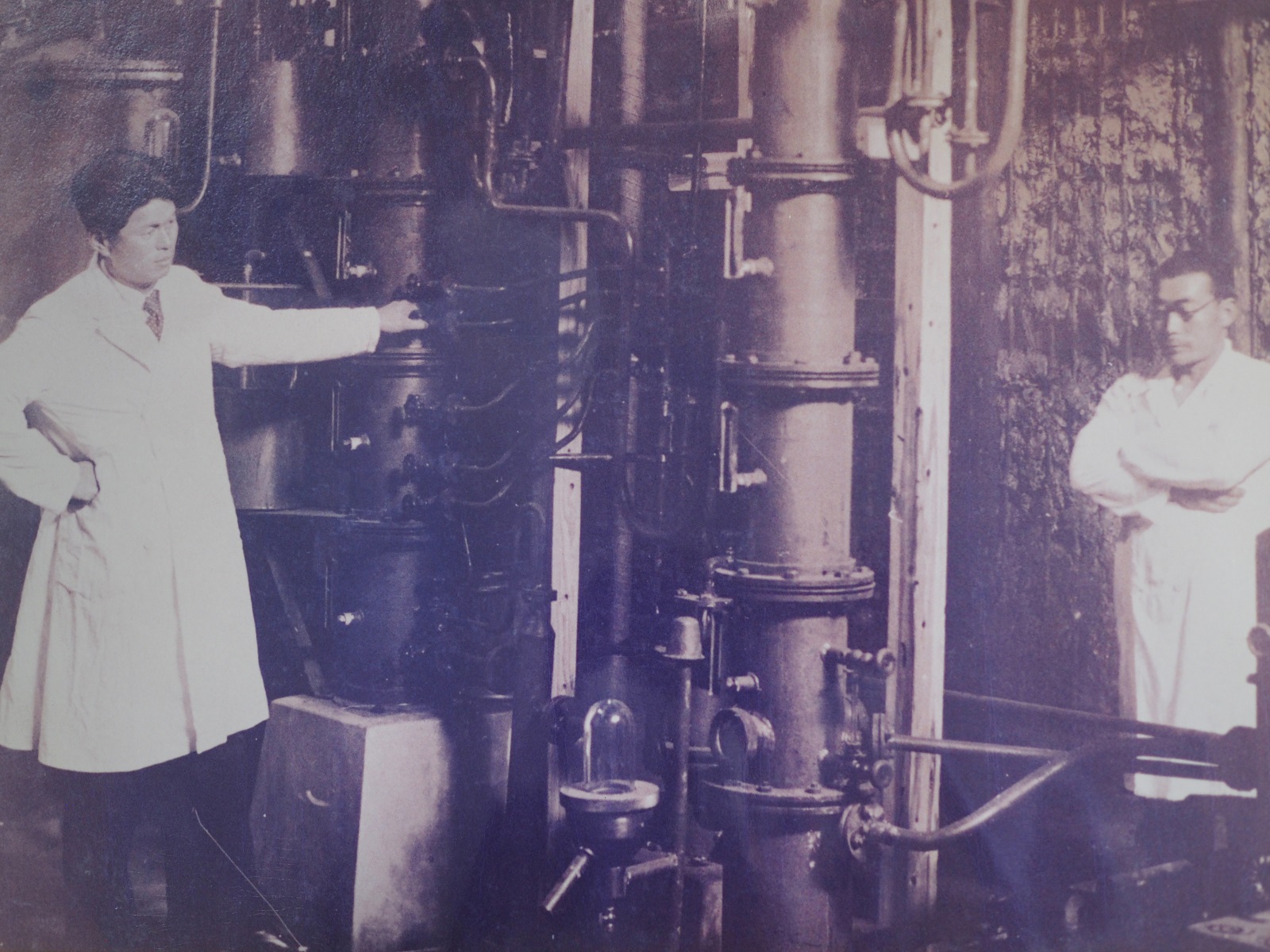
江戸時代末期の安政年間に、初代高藏氏が新潟県より酒造り杜氏として水戸に入り創業した加藤酒造店が当社の前身であり、1950年(昭和25年)に事業を継承し、明利酒類株式会社として創立しました。現在では、醸造用アルコール・清酒・焼酎・発酵調味料等を製造する酒類総合メーカーとして、着実に成長し、皆様に大きなご信頼をいただいております。
銘柄:副将軍(清酒)、漫遊記(焼酎)
サイト:https://meirishurui.com/
製造責任者:高蔵蒸留所 製造責任者 鬼澤啓一 様
Q 導入ポイントは?
2022年10月より約60年ぶりにウイスキー製造(1962年に火災で蒸留所焼失)を開始しました。そのために、ウイスキー製造での酵母醗酵温度やウイスキー樽貯蔵庫の庫内温度経過を知りたく導入いたしました。

創業は慶安3(1650)年。「伝統とは時代と変化をともにし、つながるものである」と捉え、米の旨味たっぷりのふくよかな味わいと、ピュアで軽快な余韻を感じられる日本酒を基本に、ふたつの銘柄を醸しています。酒蔵の立地、標高936mは日本一か二の高さで「日本で最も星に近い酒造」として、凍てつく環境ではありますが培われてきた寒さに強い酒造技術により、たくましくも優しさあふれる酒が醸し出されています。
銘柄:木曽路、十六代九郎右衛門
サイト:https://yukawabrewery.com/
代表者:代表取締役 湯川 尚子 様
Q 導入ポイントは?
麹室入室回数の軽減、夜間温度見回りの軽減、社員への情報共有、記帳の正確性など。

1790年(寛政2年)創業。酒米の約85%は富士川町を中心とした地元産にこだわって使用してます。地元関係者と協力し、酒づくりの方向性や想いを常に共有し、たゆまぬ努力で「おいしい酒を造るための酒米づくり」を追求。また、徹底した原料米処理こそ「うまい酒」づくりの第一歩だと考え、地元で獲れた酒米を、自ら磨く「自社精米」を実施し、納得がいくまで酒米を磨いています。
銘柄:春鶯囀
サイト:https://www.shunnoten.co.jp/
代表者:社長 長沼 慶太 様
Q 導入ポイントは?
現場の負担低減のため。

明治3年(1870)。蓬莱が追い求めるものは「米のいのちを生かすよう、真っ直ぐに醸す、心や人間性の酒造り」。伝統と手造りを重視し、古い木の道具を使い、じかに感じる香りや手触りを大切にしています。
一本一本に魂を込めて皆様に「蓬莱に出会えてよかった!」と感動していただける美酒を目指して仕込んでおります。
銘柄:蓬莱
サイト:https://www.sake-hourai.co.jp/
代表者: 代表取締役 渡邉久憲 様

当センターは,公設試験研究機関でも珍しい実規模の試験醸造設備を有しています。また,清酒の製造免許(本免許)を有しており,公設試験研究機関で唯一,試験醸造酒を独自銘柄「明魂」として販売しています。試験醸造により,新たに開発した酒米や酵母の評価,酒米の生育状況の把握,人材育成などを行い,得られた成果は技術指導に活用されます。
銘柄:明魂
サイト:
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/…
Q 導入ポイントは?
細かな品温測定によって多くのデータを取得し,酒質安定化を図る。

当センター食品技術部門は、県内食品産業等の発展に寄与することを目的として設立されています。技術相談、人材育成、設備利用、依頼分析、受託・共同研究、試験開発研究などを通じて、県内食品産業の発展に貢献いたします。今回導入したもろみ日誌の保有機材は、地元酒蔵様がご利用いただけるよう、サービスの準備を検討しています。
サイト:https://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/
Q 導入ポイントは?
試験醸造でのデータ取得効率化。

明治28年に開校し、昭和43年に国から自営者養成高等学校の指定を受け寄宿舎が設置され、農業経営者育成の教育が行われています。専門教育を通して豊かな人間性を磨き、自主性・実践力に富む将来の農業経営者および関連産業技術者の育成に努めています。水戸農業高校は、体験を通して「生きる力」を育む実り多き農の学び舎です。
サイト:https://www.mito-ah.ibk.ed.jp/
Q 導入ポイントは?
ICTを導入し、(デジタル)視覚的及び詳細なデータを取れる。学習の効果を向上させられると期待したため。